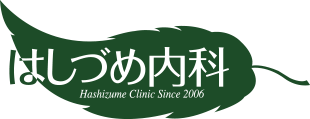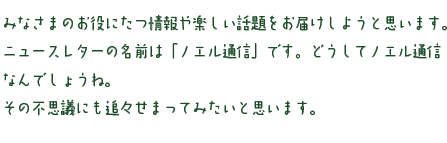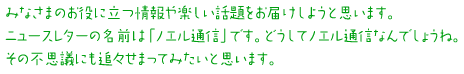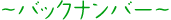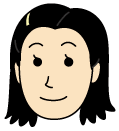
“尿について”第2弾
ノエル4で「尿路感染症」についてご説明しましたが、今回は
膀胱の機能には、“排尿”のみではなく、尿を膀胱内に溜める“蓄尿”機能があり、過活動膀胱は蓄尿の不具合が主な原因と考えられています。蓄尿機能が落ち膀胱に尿を溜めることができないため、尿意切迫感(突然起こる、我慢できないような強い尿意)、頻尿や尿漏れなどの症状が起こります
生活に及ぼす影響が大きい疾患
我が国の40歳以上のおよそ7人に1人の頻度で見られるといわれる過活動膀胱。特に60歳代からの発症率が高く、年齢とともに上昇します。
生活への影響は過半数で見られ、家事や仕事のほか、家族関係、性生活、自尊心が傷つくといった心の問題も表れ、睡眠、活力、身体的活動、社会的役割に影響を生じます。
頻尿は特に夜間就寝中に起こると睡眠が中断され、また、尿失禁を伴う場合もあり、生活に及ぼす影響が大きい疾患ですが、医療機関への受診率は、症状のある人の22.7%(男性36.4%、女性7%)と云われています。
ではどうして“尿意切迫感”が起こるのでしょうか。膀胱などの尿路機能は中枢神経系(脳や脊髄)と末梢神経系の複雑な神経ネットワークで制御されています。中枢神経は膀胱内のさまざまな部位から多くの知覚情報を受けていますが、膀胱が知覚過敏となり、それらの情報を中枢が処理できない、つまり膀胱からの神経伝達の病的亢進と、脳が伝達された情報を処理できないことが重要な病態と考えられています。そのため“尿意切迫感”は正常な膀胱が充満した感覚とは異なる病的な尿意といえます。
過活動膀胱を呈する疾患過活動膀胱の原因には、まず脳血管障害、脳腫瘍(特に前頭葉といわれる部分の障害)や脊髄損傷などの神経因性過活動膀胱があります。腰部脊椎管狭窄症や糖尿病性末梢神経障害でも起こることがあります。また骨盤内の腫瘍や尿路の結石や炎症、子宮など膀胱周囲の臓器の異常でも同様の症状が出る事があるため検査が必要です。
それ以外の原因として、メタボや生活習慣の乱れが考えられます。加齢性変化でも見られ、生活習慣病を沢山併せ持つほど膀胱の血管の老化がすすみ、過活動膀胱の症状の程度が強くなるといわれています。
尿量そのものが多い多尿や心因性頻尿、薬剤の副作用が原因のこともあります。また、明らかな原因を特定出来ない特発性過活動膀胱もあります。
治療はまず生活習慣の改善です。肥満、運動、喫煙、食事、飲水、炭酸飲料摂取、便秘など種々の生活の要因が過活動膀胱に関係するため、肥満の改善や運動、少し飲水を制限したり、カフェイン、アルコール摂取を減らしたりすると効果がみられることがあります。
尿をなるべく我慢する膀胱訓練は効果があり、約75%の方が改善したという報告があります。
① 2~4時間毎の一定の時間での排尿
② 生活に合わせ、失禁を起こす前にトイレに行くスケジュールを作る
最初は徐々に排尿間隔を伸ばすよう、リラックスして尿意をそらすようにしてみて下さい 。 一ヶ月 毎に排尿日誌を付けてみてはいかがでしょうか 。排 尿 回 数の減少 が自分で解ると励みになります。
骨盤底筋訓練尿道、肛門をギューっと 締めたり、ゆるめたりを繰り返すを併用すると、骨盤底の筋線維が大きくなり、骨盤底筋の収縮力が強化され ます。骨盤底筋が強くなると膀胱の排尿筋の収縮が抑えられ、尿が我慢しやすくなります。骨盤底筋訓練での効果は60-80%と云われています。
生活習慣改善で効果が乏しいときは、薬物療法も行っています。抗コリン薬やβ3作動薬という薬がありますが、特に高齢者では副作用に注意が必要なため、漢方が使われることもあります。
“尿具合”ついてお困りの症状は性別にかかわりませんが、男性の場合は前立腺の関係もあるため、一度泌尿器科受診をお勧めします。
参考文献;過活動膀胱診療ガイドライン第2版
(院長 橋爪喜代子)