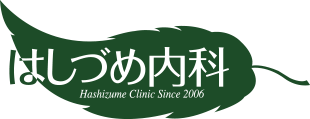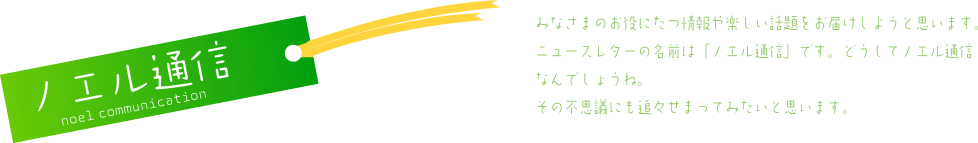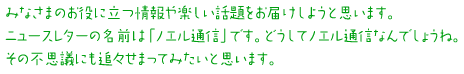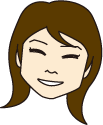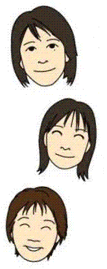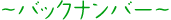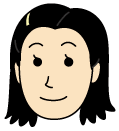
今回は尿路感染症についてのお話です。腎臓から尿管(腎臓と膀胱を結ぶ管)、膀胱、尿道(膀胱から体外に尿が排出される管)にいたる尿の通り道を尿路といいます。健康な状態では尿には細菌はいませんが、消化管内にある大腸菌などが尿道から入り込むと尿路感染症を起こします。尿路感染症は”下部(膀胱)”か”上部(腎臓)”か、”単純性”か”複雑性”か(もともと尿路系に病気がないかあるか)また年齢・性別により診療方針が異なります。女性では急性膀胱炎、急性腎盂腎炎が多いのに対し、男性は膀胱炎は少なく、尿道炎、前立腺炎、精巣上体炎など泌尿器科的疾患が多くなります。今回は膀胱炎と腎盂腎炎を中心にお話します。
急性単純性膀胱炎は若い女性に多く、排尿痛、頻尿などの膀胱刺激症状がみられますが、高熱はなく、膀胱自体の防御効果により自然に治る事もあります。通常は抗生物質の内服で1週間くらいで改善しますが、再発することが多いため、水分を充分にとる、排尿をガマンし過ぎない、お尻を拭く時は前から後ろへ、下腹部を冷やさないなどの注意が必要です。性交が原因となることもあります。膀胱炎に似た症状で感染のない場合、間質性膀胱炎(かんしつせいぼうこうえん*1)、過活動性膀胱(かかつどうせいぼうこうえん*2)のうたがいもあります。中高年では男女差は少なくなり、脳血管障害による排尿異常、糖尿病など基礎疾患がある場合では難治性となることがあります(複雑性膀胱炎)。
急性単純性腎盂腎炎は一般的には下部尿路から細菌が、腎臓の出口である腎盂というところに侵入することにより起こります。膀胱炎により、尿管が膀胱に移行する部位の弁機構が一過性に障害され、逆流して生じますが、尿路閉塞(結石、腫瘍、男性では前立腺肥大など)により尿の流れが悪い場合、上部に感染が起こりやすくなります(複雑性腎盂腎炎)。小児では生まれつき尿管が逆流しやすくなっている場合があり、小児期に尿路感染症を繰り返す場合は検査が必要です。症状は38℃以上の発熱、背部~腰部痛があり、菌血症(尿と同じ菌が血液からも検出される)、腎不全を合併することもあります。解熱するまでは抗生物質の点滴を含めた強力な治療を要し、解熱後も経口の抗生物質を2週間は続ける必要があります。複雑性腎盂腎炎では背景にある尿路異常を治さないと再発しやすくなります。
膀胱炎はよくある病気のひとつですが、腎盂腎炎にいたると入院が必要なこともあります。また、間質性膀胱炎など、より詳しい検査が必要な場合もあります。トイレの悩みはつらいですがガマンしないで一度ご相談下さい。
*1 膀胱壁の内部の間質という部位に炎症が見られるもの
*2 膀胱の知覚過敏などにより尿意切迫感が生じるもの
(院長 橋爪 喜代子)